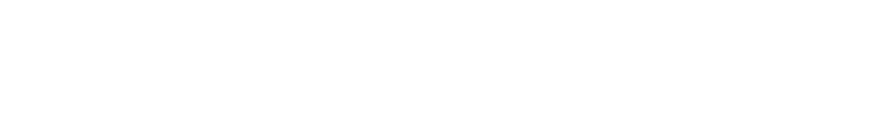本編は前々週の「創元推理文庫」の続編である。
と、いうのはいささか好奇心に鈍感になった男が600ページのそれもいわゆる、当世の小説である、舞台か映画のシナリオのような構成で書かれた本ではなく、全ページびっちりと書かれた構成の本を読んだのだから久々の快挙であったのではないか?と思った。
久しぶり、いわゆる本を読んだという実感をおぼえた感慨に浸って本書をまだ手元に置いてその表紙をしみじみと眺めている。奇しくも先々週本書が生まれた英国の新しい王様の戴冠式が行われた。ただ、この王様は間違いなく本物の王様であるが?
「ゼンダ城の虜」はルリタニアという架空の国で展開される冒険譚であり、それも英国人が誰でも興味をもつであろう王室の内側を書いた小説であり、あの時代における第一級のテーマであった。多くの英国人は当時の英国王が偽の王様であったらどうだろうか?などという奇想天外な事を思いつつ多くの人が本書を手にしたろうし、その続編を望んだに違いない。
現在では女性週刊誌しか取り上げない、いわゆる王室のテーマはあの時代の英国ではまさに第一位のテーマであり、あらゆるメディアが取り上げあげたのだろう。
日本でもかつてそんな時代があった気がしている。今から30年くらい前の話、日本における王室にかかわる話として九条武子について調べたことがあった。今でもその頃に読み漁った九条武子に関する本が10数冊が扉付きの本棚の奥に鎮座している。
私の母の時代には知らない人はいないその人は今でいうところの秋篠宮眞子さまのような存在だったような人であったのだろうか?正確に言うと天皇家に近い存在ではなく、いわゆる華族の一員であった。ただ、九条武子さんは西本願寺の門主の姫君であり、その女性が公家の中でも筆頭の九条家の御曹司と結婚、この御曹司がイギリスのケンブリッジ大学に留学した際に新妻である九条武子を10年近くほったらかしてイギリスから帰らず、宮内庁が世間の心配、好奇の力に押されてイギリスに職員を派遣したところ九条武子の旦那?はイギリス人女性と結婚して、子どもまでいたという現実に直面し、国家的な問題になりそうな状況を回避するためにそのイギリス人女性と秘密裏に別れさせて、旦那である九条良致(くじょうよしむね)を強制的に帰国させたというスキャンダルに発展した話である。
その背景には九条武子は著名な歌人でもあり、その夫を日本で待っている心情を切々と歌った歌集「無憂華」がベストセラーになり、誰もがなんでこの旦那は帰ってこないのだ!との思いが日本中に満ちたようで、その不貞の旦那に好奇の目が注がれたのであった。
小室君&眞子さまとは違った展開だが、アメリカの弁護士試験に落ちた、受かったという話題より、今、読んでも九条武子の歌は切なく、多くの女性を惹きつけただろうと思われる。
そう考えると当時の皇室関連は何とも文学的な香りがあるが、実はその裏には九条武子の旦那にも言い分があったようで、その結果、九条良致はそのような行動に走ったのではないか?というような事もあったようである。その話をするとキリがないのでこの辺で終わらせるがこれも一種のルリタニアロマンの話のようである?
その流れから以前、私は京都に行った際に大谷本廟の九条武子さまのお墓を訪ねたくらいなので九条武子さんは私とってフラビア姫のようなものかもしれなかった?
本題に戻ると創元推理文庫の「ゼンダ城の虜」の第一部は「ゼンダ城の虜」、第二部は「へンッオ伯爵」に分かれており、第二部は第一部の続編であるが、これは熱烈な愛読者の要望にアンソニー・ホープが応えたもので、ヘンッオ伯爵とはいわば本書の悪役のトップの人物で主役の仮の王様は最後の最後までこのヘンッオ伯爵と死闘を繰り広げる。
架空の国であるルリタニアに関して思うのは国のモデルはどうも、オーストリア・ハンガリー帝国なのではないか?というのはこの帝国のゴタゴタ劇は多分、王国好きの英国人好みの格好のテーマであり、リアルに進行する事実とそれをシンプルに分かりやすく、こうあってほしいと思う英国民にとってはまさに単なるおとぎ話でありながら、リアルな世界の未来を先取りするような物語でもあったようなのだ。
ルリタニアのモデル国でもあるオーストリア・ハンガリー帝国は第一次世界大戦で敗北し1918年に消滅するのだが奇しくもこの年に作者であるアンソニー・ホープはSirの称号を授与されたのが何とも意味ありの授与のような気がしないではない。
いずれにしても現実にこの戦争である第一次世界大戦は第二次世界大戦を引き起こす萌芽を持っていたのだからアンソニー・ホープの文学ほど美しい結末にならなかったようである。いずれにしてもこれを機にヨーロッパの国々の王家について知ると門外漢が簡単に感想をかけるような世界ではないことが分かる。
ただ、「ゼンダ城の虜」想像以上に面白いことは確かであり、推奨したい本である。
2023年5月22日T.I