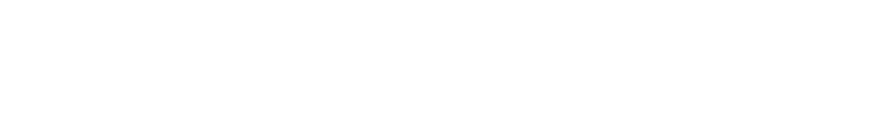アルバムというモノは洗濯板と同じように死語、死物になりつつある。だが、洗濯板はそれでもいいがアルバムはそうではないだろうと思う。
アルバムを構成するのは紙の写真とそれを貼り付けるノート状のもの。この言葉、何語なのかと調べるとalbumはラテン語の「石灰」を意味してそこから「白い掲示板」を意味するようになったらしい。したがって、大学ノートでもアルバムになりうるようだ。しかし、アルバムは大事な思い出のため、もっと堅牢な専門のノートになっている。
いつしかそれが面倒なので、スマホが勝手に保存するようになった。モノではなく、記録媒体としてアルバムが確立した。しかし、これが便利なようで、そうでもない。
前考のAsahi Weeklyで昔、ヨーロッパに頻繁に出かけた話を書いたが、実際、その頃はスマホがなかったのでカメラ持参で出かけた。最初の頃は一眼レフ、それ以後は小型のポケットカメラ、それからはチップを入れる電子カメラ。電子カメラはDPEの店頭でそのチップを紙焼きしてもらうことになる。いずれにしても紙写真にしないと楽しめないのだ。アルバムはその紙写真を張り付けて本にするものである。映像記録をノートに貼り付けて残すものである。
その昔、ヨーロッパに頻繁に出かけた時の写真を家人がアルバムに旅行ごとにまとめて貼ってくれた。その数は20冊に近いので、毎年2回出かけたので10年のヨーロッパ旅行記になる。テレビの「ヨーロッパ街歩き」を見ながらジュネーブのアルバムを拡げた。まず、アルバムを滅多に開くことがないので、こんなところに行ったのだ?ということと昔は髪の毛が多かったな?と言う印象が第一になる。かみさんも若いな、娘も小さいな?そんな当たり前の実感とともにページをめくる。ともかく人生の記録なのだ。
追憶の瞬間が無限に広がる。この小さな家族だけの。この堅牢なノートの価値は3人にしかないものだ。そして、その街とともに3人の記憶の中に刻まれる。アルバムは確かに記憶媒体である。(媒体のバイの字の意味は仲立ちをするという語義、この語の音のバイは梅からきているらしい?驚きの経緯で成り立った漢字である)
老人には追憶と言う語がふさわしい。どんな人でも76年も生きれば、それなりの思い出があるものだ、しかし、その追憶が心地よいものであったなら幸せな人生を送った人と言えるだろうが、たとえ心地よくない追憶でも歳を取ると、そう生きた証として変化してくる可能性がある。過去の都合の悪いことでも、解釈次第ではそう悪いことでもないような気がしてくるからである。
昔、社内報(モートピア)に何かエッセイを書いてくれと編集委員にお願いされて「追憶の都」という題のエッセイを書いた。スペインを旅行した時の話を書いたのである。
何でスペインが追憶の都と呼ばれるのかわからない、何かそのようなテーマの文学作品や映画でもあったのか?ただ、何となく思うのはヨーロッパの一国でありながらスペインはピレネー山脈で大陸と切り離されており、それゆえ、大陸で自分に起きたいろんなことから逃れてくる人がそれぞれの思い出を浄化するような場所だからなのではないかと?
アランフェス協奏曲の有名な第二楽章の旋律が全てのような気がする。アランフェスの宮殿に出かけた時,観終って広場のテラスにあったカフェでその広場を眺めていた。その時、一陣の風が広場の乾いた土を巻き上げた。一瞬、ロドリーゴのその旋律が頭の中を駆け巡った。そして、盲目の彼はその体験をした気がした。
何年か前に「リスボンに誘われて」という映画を観た、あまりにも良かったので原作「リスボンへの夜行列車」を読みたくなり図書館で本を借りた。小説でありながら歯が立たない本であった。これがヨーロッパでベストセラーになったことを知って、オレの知的レベルもその程度かと思って腐った。しかし、映画は地味な映画だが素晴らしかった。追憶に追憶を重ねた映画である。ポルトガルも追憶の都なのであろう。
2022年10月31日