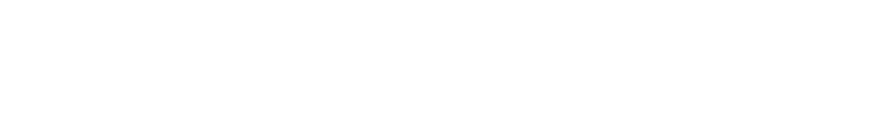私は趣味で小説を書いている、無名の売れない小説家?で書いているものは文学といえまい。どうみても通俗小説のような気がするからだ。
しかし、そのあたりの境界がはっきりしない。というわけでそれを納得するために芥川賞をとった作品を読んでみようと思い手始めに中山義秀の本を読んでみた「厚物咲」という本である。初めて聞いた人の本である。
なぜ、そんな本を読んだのかというとかれのお嬢さんが書いた「鎌倉極楽寺九十一番地」という本が鎌倉文士であり、芥川賞作家であった父、中山義秀論のような本だからであった。私はそれまで中山義秀という作家を知らなかった。
読んでみて松本清張の「ある小倉日記伝」を読んでいる気がしないではなかった。なんとなく行き場のない内容の本で、何か考えさせられる小説であった。面白いが、何とも言えない、初めての切り口を持った物語とでも言おうか?ただ、双方とも暗い物語である。読後感にやり場のない人間の物語という感があるのだ。
双方の受賞傾向が時代性にあるのではないのかと思い年代を調べると松本清張の方は1953年受賞、中山義秀の方は1938年受賞でその差は15年、違いは戦前と戦後の小説であるということだ。
どうしようもない読後感は双方共通しているが、作品としては「ある小倉日記伝」の方が面白い。というのは少なくとも基本的な要素に客観性があるからだ。中山氏の方は菊の栽培というまったくマニアックな世界について、誰も知らないし、興味を感じないテーマであり、タイトルにある「厚物咲」ということがどのように優れているのかも分からない中でそれを実現させて首を括るという理由も不自然な感じがしたのである。
それに比べると森鴎外が軍医として小倉に転属になった際の3年間の日記が無いという空白の現実を再現したいという発端は理解できる。というのは身体的障害のため多くに人から蔑まされていた主人公がいわゆる常人に対して一矢報いる挑戦でもあったからだ。
その彼が丹念に調査し再現しようとする努力のプロセスは身体的弱者に対する松本清張のヒューマニズム的ミステリーのような面白味があってぐいぐいと物語の中に読者を引き込んでいく。その筆力は新人にしては名人の域に達している感があった。
小倉日記伝を再現しようとする当人は今でいう身障者なのでその調査を阻む人々の蔑みなどを乗り越えて完成に近づくがその無理が主人公の命を最後には奪う。彼の死後、鴎外一族により鴎外の書いた小倉日記が発見される。読者は彼が命をかけた小倉日記伝は何だったのだろうか?という無常観と本質的な問いを突き付けられたまま物語は終わる。
これが芥川賞の作品で新人の作者に贈られる賞だとしたら驚くべき作品である。正直、今でもその読後感は忘れることはできない。
この二作品は今から70年以上も前の作品なので時代も変わり、芥川賞そのものも変わってきているのではないかと思い、もう少し現在2023年に近い作品を読んでみるかと思い。興味を引くような本を探して何を読むかと考えた末、一時、三島由紀夫の再来といわれた平野啓一郎でも読んでみるかと思い話題になった「日蝕」という本を借りた。というのはなんとなくこの本が若い作家の中で正統派の芥川賞らしい作品であるという、気がしたからであり、当時、かなり騒がれた気がしたからだ。
しかし、読み始めて数ページで読むのをやめてしまった。というのは小説の原点であるコミュニケーションという点で際立って難点がある本だったからだ。何年か前にすべてカタカナで書いた本が芥川賞をとったがその時もそれも文学における先進性への挑戦の証か?と思ったが「日蝕」はその先鞭をつけたような作品であるようなのだ。
「厚物咲」にしても「ある小倉日記伝」にしても小説の基本である物語としても面白さがあり、読者が苦労するのはそこに書かれた内容の深さに考えさせられる苦労があるからであり。決して難しい漢字や衒学的な言い回しや、外国語で苦労をすることではないからである。そうやってみると年に2回も芥川賞受賞者が出るという、その現実を再考しなければならない時期に来ているのではないか?
ショパンコンクール並みに5年に一度でランキングを付けるなど工夫をしないとマンネリ化して芥川賞自体の価値が失われる気がしないではない。
2023年7月17日T.I