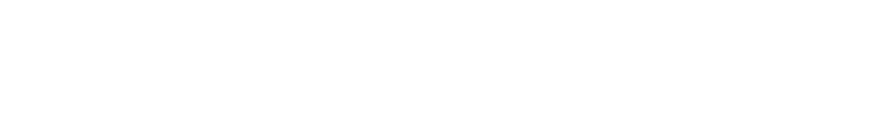私と同じ範疇の人がとんだ社会的問題を起こしたという点で注目すべき事件である。
私の範疇というのはいわゆるマーケティング戦略を立案することを外資系の会社で生業にしていた人という点で同じような範疇という意味である。また、昨日その問題の人物のキャリアが紹介されたが、当人は外資系のトイレタリー、もしくは化粧品メーカーにいたというから何となく想像がつく会社である(P&Gであったようだ)。そのキャリアで吉野家牛丼チェーンのマーケティング部門に転職したというケースでこれもよくある話である。
一般的に外資系のマーケティング部門というのは確かに日本企業のマーケティング部門より、まあ、洗練されており革新的な最新の手法を使い実績を上げているので、その経験を生かすことができるスタッフは高い給料を支払っても採用することは十分に見合うことと考えられている。
今回の事件の特殊性はそのようなマーケティングマンを教育する大学の講座の講師として採用してそれこそウブな生娘のような(それにしても品のない言葉である)学生?に教えていたという問題である。なんとなく小学校の教諭が児童を隠し撮りしていたことと似た行為を大学での教育という名目で行われていたという問題であろうか?
この事件がクローズアップされて本人が在籍している吉野家もそのかれを採用していた早稲田大学もとんだところの失態でその対応を早々に発表したが、多分、本人は今在籍している吉野家(ここでは常務取締役)という肩書なので一般社員とは違う立場?なので今後の動向は分からない?居直って粛々と在籍し続けるか、辞表を出すか?解任されるか?
それにしても外資系の会社というところに在籍をしていたという点が事件の本質にあるような気がしている。というのは外資系のマーケティング部門では多分に業績に寄与することならば何でもOKという気風があるからだ。そして、マーケティングにおける成功(売上向上)の鉄則は新しい試みを成すことであり、そこに成功の鍵があるからだ。(しかし、外資系の会社は一般的な社会倫理に関する教育を徹底的に行うので、こんなことは特殊なケースであると外資系の会社を経験していた方が語っていたが?)
だが、「生娘シャブ漬け戦略」は概念としては全く古典的なマーケティング原理である。というのは私が会社に入って学んだ最初のマーケティング戦略の基本概念が生娘シャブ漬戦略(略称KSS?)だったからだ。というのは私がデザイナーとして就職した最初の会社はホンダグループの子会社のホンダランドという会社で鈴鹿サーキットや多摩テック、朝霞テックなどを運営している会社でそこで使用している乗り物やレジャー用車両及び遊戯施設を開発している会社であった。
この会社をつくったのはホンダの創業者の一人である藤沢武夫副社長でその理由が素晴らしかった。つまり、遊戯施設と言ってもこのホンダの遊園地の目玉はジェットコースターなどではなくゴーカートであった。楽しみの原理的はジェットコースターとゴーカートは全く違う遊戯施設である。ゴーカートは子ども自身が自ら主体性を以て楽しめるものであり、ジェットコースターは乗せられて楽しむものである。
藤沢武夫は鈴鹿サーキットや多摩テックなどを造った理由をこう語っていた。小さな子供が自分自身で操ることができる最初のエンジン付き自動車は(ホンダの)ゴーカートである。子どもにとってその驚きの体験は生涯を左右するものだ。多分、大人になってもモータースポーツを愛する人になるに違いない。そのような人たちがいてHONDAが成り立つのだと。
したがって、ホンダのゴーカートを体験した子どもたちはティーンエージャーになったらホンダのオートバイを選ぶであろうし、家庭を持ったらホンダの四輪車を買うに違いないと・・・・これをかのマーケティング講師に言わせれば究極の「HONDAシャブ漬け戦略」と命名するであろう。この方法は私の経験から言う究極のブランド戦略ということになる。人生がHONDAブランド と共にあるという事なのだ。
たしかに信頼できるブランドがあるということは人生を幸せにするだろう。育ちの良い家庭では三越というブランドと共に三世代、四世代と共に確かで豊かな人生を歩ませていただいたという思いがあるかもしれない。
かの講師もこのような例を引きながら説明すれば有能な講師として恙なく済ませられたのかもしれない。しかし、かれはこうなることを予想しての今回の行動だとしたらこれはこれで、また見事なインパクトマーケティング戦略だったのかもしれない?
しかし、この言葉を聞いてだれもがいやな、印象、そして反社会的な印象を持ったのである。そして、だれもが拒絶する拒否感を感じるような、女性を蔑んだような、感じが誰もが感じたのだろう。一般的なマーケティングマンでなくともそのあたりは直感的に分かる気がしないではない。本来、このような話は超内輪のこの手の人たちの覆面ブレーンストーミングで出るワードかもしれない。そのような場では笑いで済ませる業界内の位相語ならぬ、位相ワードなのだろう。
かれはもしかするとマーケティングを学ぶ学生をそのような業界人と勘違いしたのかもしれない。しかし、その言葉に腹立たしさを覚えた学生は憤慨するのは当然だ。今の時代それがあっという間に拡散する。そう言う時代であることをそのマーケティングマンが分からなかったとしたら、私に言わせればそれこそ憤慨ものである。
インパクトのある手を打ってでも売り上げを向上させるという宿命を担わされているマーケティングマンはそのような危険と背中合わせで仕事をしているのかもしれない。
2022年5月2日
もう少し真面目なマーケティングマン記