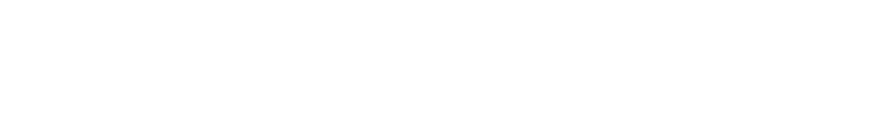ビンシャーマン氏が亡くなったことを朝刊で知った。100歳である。私が彼の演奏を聞いたのが今から50年近く前のことだから、その間、彼はバッハをどのくらい演奏したことであろうか。彼のバッハはいつも活き活きとしており躍動的で、元気をもらえるようなバッハであった。
彼に関して特別な想い出があるのは彼の演奏会でのアクシデントゆえである。たしかバッハのオーボエ協奏曲へ長調の演奏中の時であった、それは第二楽章で起きた。朗々たるその曲のクライマックスで突然、彼のオーボエが異音を発した。それは初めて聞く人もそれがバッハの書いたものではない音とわかったであろう。かれはすぐに手を上げて演奏を止めた。そしてすぐに自分のオーボエにアクシデントが起きたのでお待ちくださいと言ったようだ。ドイツ語だから分からない。かれはステージの後ろに消えた。そこには技術者がいたのかもしれない。少したってから何も持たずにステージに現れた。そして、観客に向かって事情を話して申し訳なさそうに何度も頭を下げてお詫びをした。
そして急遽、その内容は日本語でアナウンスされた。「どうするのかな?代わりのオーボエは持ってきていないのかな?」などと考えたが、ビンシャーマンのことだから最高のオーボエで最高のバッハを聞かせたいと思ったのだろう。代わりのオーボエなどあるはずがない。そして急遽代わりの演奏になった。そのときの合奏を担当していた首席ヴァイオリン奏者がバッハのヴァイオリン協奏曲を弾くことになった。指揮は勿論ビンシャーマン自身である。正直に言うがその演奏がまた見事であった。かれは急ごしらえのビンシャーマンが決めた曲目のすべてを完璧に演奏した。
私をはじめ、多くの観客はその思わぬ展開をスリリングな体験として楽しんだのではないかと思う。それにしてもソロの奏者でもないいわゆるコンサートマスターともいえるヴァイオリン奏者の技量の驚いたのだ。
今から考えると50年近く前のその頃は異常乾燥の期間が長く続いた気がしている。木の楽器である乾燥したオーボエはそこに湿った息が吹き込まれ楽器本体に何か異変が起きたのだろう、割れたとか何か?リードなら予備を持っているだろうから交換は簡単である。しかし、本体が割れては演奏は不可能である。
ビンシャーマンはドイツ・バッハ・ゾリステンという自分の楽団を結成し、世界で音楽活動をしていた。いわゆるバッハ音楽のスペシャリストであった。バロック音楽の室内楽はそんなに多くの演奏者たちを必要とはしてないジャンルだったので、かれらはみな自分の楽団を創り活動していた。また、お抱えの楽団を持っていた。クルト・レーデルとミュンヘンプロアルテ合奏団、カール・リヒターとミュンヘン・バッハ管弦楽団、アウグスト・ヴェンツィンガーとバーゼル・スコラ・カントルム、それから、かの有名なニコラウス・アルノンクールとウィーンコンツェント・ムジクスなどである。
ビンシャーマンのそれはバッハという大家の音楽をビンシャーマンの味付けで演奏するというような楽団であり、そこには小うるさい理屈や解釈などは抜きにしてビンシャーマンの個性によるバッハというのが売りの様だった。その点において彼はバロック音楽のジョン・ウェインのような感じであった。ともかく健康的で楽しいのである。カール・リヒターのように厳格で一点の隙もないバッハではない、対極にあるバッハのような気がしたものである。
本考を書くにあたり、彼のその後の活動を調べるとあの巨大なマタイ受難曲やヨハネ受難曲なども振ったと書いてあったが老熟したビンシャーマンが行き着いた一つの境地であろうなとの思いをはせた。100歳まで生きたというのがいかにもビンシャーマンらしい、たとえば同じバッハの指揮者であり演奏家であったカール・リヒターは指揮者としての絶頂期の55歳に心臓麻痺で客死しているが彼のバッハを聴くとそれも頷ける何かがあるような気がしないではない。
私はカール・リヒターが初めてミュンヘン・バッハ管弦楽団と合唱団を率いて来日した時、オルガン演奏とロ短調ミサを聴きに行った。その時に想い出すのはかの有名なトッカ―タとフーガの最初の音をミスったのである。そのことは当時、専門家の中でもかなり話題になった、識者はそこに深遠なリヒターの意図を読み取ろうとしたようだが初心者の私はどう聴いてもあれはミスだ、と確信したものであった。真実はリヒターのみがしることである。ただ、音楽的にそのミスをした音は何ら違和感がなかったのが不思議な気がしたものである。
その後、私は音楽とは無縁の生活を送ったが唯一演奏会に行ったのはやはり、古楽器の演奏会であったフランス・ブルッへンがモーツアルトの「フリーメーソンのための葬送曲」を演奏するというのでこれだけは聴き逃すわけにいかんと思い出かけたのである。この時の合奏団は忘れてしまったが彼が率いてやって来た古楽器の楽団であった。このフリーメーソンの曲はモーツアルト自身の葬儀のためにかれが作曲したものと言われている。モーツアルトの死と直面した音楽はみな深遠で、胸を打つ。あの厳かさは筆舌に言い表せない。この演奏会で一番印象的だったのはいくら拍手をしてアンコールで戻ってきても決してアンコール曲を演奏しなかったことである。何ともケチな指揮者だな思った。
私の音楽の世界はここまでである。かれらが生きた時代が好きであり、その時代を蘇らせてくれるのがかれらの音楽なのであった。その時代がどんな気分を持っていたか分からないがビンシャーマンにとっては底抜けに明るい時代であり、音楽はそんな気分を盛り上げてくれるものであったのではないかと思う。神は常に人々と共にあり、何かと世話をやいてくれたのだ。音楽を聴きながら神と人々は共に向かい合って語らったのだろう。ヘルムート・ビンシャーマンは多分そんな世界に旅立ったに違いない。
泉 利治
2021年3月8日
ヘルムート・ビンシャーマン
21.03.08